【旧作百円】古い映画が面白い!【TSUTAYA】
最近気に入ってるブログがあって、古いアーカイブをちょこちょこ読んでいる。「映画に 乾杯!」
どんな人が書いているのか、よく知らない。法制史か何かの研究者で、英語ができる、五十代のおそらく男性、というくらいしかわからないが、非常に面白い映画ブログだ。僕は副島隆彦の映画評が大好きだったのだが、最近はそういうものを書かないので淋しく思っていた。長いエントリが多いけど、“解読する楽しみ”“共感する喜び”に満ちたブログなのだった。
ちょうど今、TSUTAYAがDVD旧作を百円でレンタルさせるキャンペーンをやっている。珍しくまとめて何本か見たので、感想をメモしておきます。
TSUTAYAの旧作百円セールはとても良いと思います。良い映画に巡り会うと、なんだかとても元気が出るので。何が「良い映画」かってのはちょっと難しいけど。

◆「スタンドアップ」(2005)NORTH COUNTRY
最近シャーリーズ・セロンが気に入ってるのだが、この人はお金儲けのためのエンタメ大作にも出るけど、地味でハードな手触りの作品にもよく出てる。アカデミー・ベストアクトレスを獲ったのが「モンスター」(2003)で、身体を張った演技のできる人だ。評判を聞いて借りたのがこれ。
カナダと接する北国・ミネソタの鉱山が舞台の、30年以上前のセクハラ・労働問題・法廷闘争もの。
こんな古い話題をいまなぜ?と思う人もいるだろうが、これがなかなか現代的なテーマなのだ。男性ばかりが働いていた鉱山に女性が進出し、セクシャルハラスメントが起きる。女性にとってはセクハラが問題だが、男性にとっては既得権が脅かされる、その不安が男性をセクハラや男性性の誇示に走らせるという悪循環になっている。この映画に描かれる人びとの苦しさは、近年の、市場のグローバル化・労働のダンピング・雇用の不安定化・アイデンティティやメンタルヘルスの危機などにぴったり符合する。ハラスメントで会社を訴える、ということがいかに大変か、当時も今も全然変わってないと思うよ。
法廷劇としてのポイントは、原告側にクラスアクション(集団訴訟)が成立するか否かという点。個別的な民事賠償請求ならば平気だが、クラスアクションが認められると賠償は巨額になり、判例として全国で通用する大事件になる、らしい。「エリン・ブロコビッチ」(2000)で有名になったアレね。しかし「スタンドアップ」は「エリン…」とはだいぶ肌触りが違う。2000年当時は、“シングルマザーがひたむきな努力と人柄で大企業に勝って大金ゲット”というおとぎ話を素直に楽しめた。けど今は、セクハラ訴訟は一段落したけど、次は会社の存続が問題になり、最後は雇用先の危機によって町中(国中)が不幸になるかもしれない、という不安が残る。状況はつねに変化している。
映画自体は、重厚な描写、緊迫する法廷劇、かなり大きなカタルシスなど、非常に楽しめる出来。セロンも良いし、助演のウディ・ハレルソンが良い(珍しくインテリ役をやっている)。映像・音楽(グスタボ・サンタオラヤ!)も良いよ。

◆「あの日、欲望の大地で」(2008)THE BURNING PLAIN
続けてセロン主演作。文芸調の悲しい恋愛映画。助演がキム・ベイシンガー、ジェニファー・ローレンス。
海辺のレストランに切れ者の支配人の女(セロン)がいる。けど、行きずりのセックス癖等、投げやりな私生活。もう一つとの時間軸で十数年前のニューメキシコが挿入される。不倫が止められない母(ベイシンガー)と、それに気づいた娘(ローレンス)。密会場所のトレーラーハウスが不審火で燃え落ち、母親は不倫相手と焼死する。傷ついた娘は不倫相手の息子と恋に落ち、話が家族の葛藤、不倫の遠因、不審火の正体へとさかのぼっていく。
うーん、何て言うか、「マディソン郡の橋」(1995)にトラウマをひっつけたような痛い恋愛映画。あまり得意じゃない。けど、ニューメキシコの田舎の人たちの描写や、何と言っても助演のローレンスが美しかった。ローレンスは主人公セロンの数年前の役なんだけど、これがとっても美人で良い。若いから、今だけの美貌なのかもしれんが、セロンも、往年の美女ベイシンガーも食われちゃってます。

◆「ウィンターズ・ボーン」(2010) WINTER'S BONE
ジェニファー・ローレンスを見たいがために、旧作じゃないのに借りてしまった。全編ローレンスが出ずっぱりで、ファンにはたまらない!と言いたいところだが、それが全然そうじゃない。色気、皆無。
なぜなら、舞台がミズーリだかどっかの山深い田舎で、しかも冬なのでずーっとごわごわの上着を脱がない。若々しいはずのヒロインが、幼い弟妹を世話する重圧から、すっかり所帯やつれしてしまっている。
その代わり、アメリカの田舎の不気味さが余すところなく描かれ、そっちのファン――「悪魔のいけにえ」(1974)やフォークナーの小説「サンクチュアリ」が好きな人――にはたまらないと思います。ヒロインの少女は、家を保釈金の抵当に入れたまま行方不明になった父を探す。出廷しなければ唯一の資産である家と森が奪われる。だが父の容疑は覚醒剤製造で、近所や親戚とも関係した犯罪で、みんな口が重い……。
「チャイナタウン」みたいな人捜しものは、サスペンスの主要なジャンルだと思うけど、この作品はしんどいです。画面が暗く、彩りがなく、カタルシスもない。ひたすら、アメリカの田舎の殺伐とした気配に満ちている。こんなに荒涼とした土地・人びとがいるんだ……という感動を覚えた。絶対行くことはないだろうから、数百円でこの空気に触れられたのはもしかしてラッキーかも知れない。
同様のタッチの作品に「フローズンリバー」(2008)があるけど、同じ年の作品だね。思いっきりバッティングしてる。けどどちらも高評価。世界が重苦しく、不景気になりつつあるのが、映画にも反映されているみたいだ。
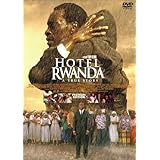
◆「ホテル・ルワンダ」(2004) HOTEL RWANDA
河本準一一件で思いついて、借りて観た。公開当時には飛行機で見ただけだったので、改めてしっかり見るといろいろ発見がある。この映画、住民が住民を虐殺するという極限状況を描いているのだが、画面にはそれが直接出てこないし、ぼーっと斜めに見ていると“主人公は仕事で忙しくするかたわら、夜は奥さんと親睦を深めている”の繰り返しに見えてしまう。不思議な映画なのである。
ドン・チードルの主人公がずーっと東アフリカ訛りの英語を喋っていたのがすごいと思った。僕は一度だけケニヤに観光旅行に行ったことがあるのだが、まじ英語のアクセントこんな感じ。イギリス・イタリア・南ア合作映画だけど、監督はイギリス人。イギリス人には、アフリカのこの辺りについて、今でも「元はうちの庭」という意識があるのかもしれない。いろんな葛藤があるだろうに、丁寧に映画を作っていて好感が持てる。ぼーっと見てるとよくわからない映画だけど。
アフリカはとても気になる地域なのだけど、日本ではアフリカについての情報はとても少ない。だからアフリカが舞台ってだけでも「第9地区」(2009)や「インビクタス」(2009)は好きです。だけど、これらに登場するアフリカの風景も、アフリカの現実のほんの一面でしかないことが、「ジョニー・マッド・ドッグ」(2007)JOHNNY MAD DOGとかを見ればわかる。これは、リベリアと思しき国の内戦、子ども兵士たちを描いた悲惨な作品。AK47がたくさん出てきて、ばんばん発砲している。これ見ると、武器へのロマンなどが軽く吹き飛ぶ。ハリウッド映画では銃器がかっこよく描かれるけど、実際には、こういう、ただの汚れた道具なんだ、というね。
ルワンダで隣人を殺した人たちも、「ジョニー…」で隣人を殺し女性をレイプした少年たちも、とくに狂った人たちではない。むしろ“自分は正しいことをしている”と信じ切っていた。ネットを炎上させる人・炎上に集まる人たちも、とくに狂ってはいない。そこが恐ろしいと思う。

◆「アメリカを売った男」(2007)BREACH
実在した情報漏洩者ロバート・ハンセンの事件の映画化。この事件が起きた2001年、僕は前半はすごく忙しく働いており、後半は鬱病でぐったりしていたので、この事件のことはほとんど記憶にない。911の半年前に露見した事件だ。
主演のクリス・クーパーが大好きだ。「アメリカン・ビューティ」(1999)の狂気を湛えた隣人将校でこの人の顔を覚え、以来、「パトリオット」(2000)「ジャーヘッド」(2005)「シリアナ」(2005)と軍人・官僚がはまり役。今回は大物FBIアナリストということで、ねちょねちょした気色悪い演技にいっそう磨きがかかっている。
本物のFBIの人がどういう暮らし方なのか僕は知らないが、こういう本を読んだことがある。『ダンナ様はFBI』。元FBIエージェントと結婚した日本人女性のエッセイだが、FBIで鍛え上げられたアメリカ白人男性がどういう行動指針を持っているかがわかって、とても面白い。面白いというか、不気味すぎる。
クーパー演じる大物アナリスト・情報漏洩者の日常の描き方が良い。組織に抱いている不満、性的な変な癖、部下の心理を弄ぶ様。彼のただ一人の部下は、実は彼を監視するFBI上層部から送り込まれた逆スパイなのだが、若く未経験な部下との騙し合いも見どころだ。
彼は合衆国の対ロシア諜報網などの情報をロシア側に漏らし続けたのだが、その動機は語られない。物語終盤で「金か」「自尊心か」などとはぐらかすようなことを言うが、明示されずに終わる。そこがまた良い。人はなぜ通報者になるのか。いや、通報者になるよりももっと多いのが“内通者”“情報提供者”だ。“ディープスロート”だの“インフォーマント”“ネタ元”だの、いろんな呼び方があるけど、あなたのすぐ身近にも、よその組織に内通者を持った人がいるはずだ。あるいは、あなたのそばに内通者がいて、あなたを含む組織の諸々をよその誰かに洩らしている。そして、彼らはその見返りに金をもらったりはしていない。ほとんどの場合、動機は金ではない。多少の飲み食いが付随することはあるけれど、人は“自分にメリットがあるから情報を漏らす”のではないのである。
人は、やむにやまれず、どうしようもなく、救われようとして、情報を漏らす。“情報を漏らす”とは、身近な誰かを他人に売る、ということだ。そこが恐ろしい。
この映画は、ある種モンスター的な人物を描いているので、そこには“内通者に共通する普遍的な何か”はあまり描かれていない。だが、彼がモンスターだったから内通者になったのか、内通者になったからモンスターになったのか、そこも描かれていない。それが良いと思う。若い未熟な部下を演じたライアン・フィリップも良かったけど、内通者をアゲるチームのマネジャーを演じていたローラ・リニーがすごく良かった。リニーは他の作品でも見て気に入ってたような気がするが、どの作品だかわからない。申し訳ない。

◆「扉をたたく人」(2007) THE VISITOR
すげー地味な映画。名脇役リチャード・ジェンキンスが初主演で大評判、というが、全然知らん人だ。見たことあるだろけど、覚えてない。
妻に先立たれたしょぼくれた大学教授が、偶然、不法就労の外国人カップルと出会う。パーカッショニストのシリア(元はパレスチナらしい)人男性とセネガル人女性。教授の、こわばって凍てついた心が、若い人たちとの交流で徐々にほぐれていく。だが、太鼓を通じて友だちになったシリア人青年が、ある日不法滞在がバレて収監される……という、日常に根ざしたリアルなサスペンス。
この映画、徹頭徹尾、地味。低予算だし、主役はものすごく寡黙で年寄り臭い演技をしているので、画面の躍動感がべらぼうに少ない。それだけに、ドラムを叩くシーンなど数少ない“動き”のあるシーンが美しい。
青年が収監された後、青年の母親が登場する。年取ってるがエキゾチックな美人。教授の硬直した心がほぐれ、躍る。このへんの変化は、それまでのスタティックな演技の積み重ねと対比され、とても生き生きと目に映る。
教授は、不法滞在者を収監する施設に面会に通い、青年の母親とも温かい交流をするが、結末はとてもリアルなアンハッピーエンドになっている。観る者のストレスも大きく、救われない不全感、憤り、哀しみを感じる。これがまた、主人公たちの感情とぴったり添っていて、うまい具合なのだ。心憎いつくりになっている。
全然スカッとしないけど、なんだか満足する映画なのだった。
ここまで挙げてきて、娯楽大作を全然見てないなー、と唖然とする。大作ってちょっとついてけない映画が多くなったんだよね。年だね。
ここで挙げている映画はだいたい低予算の、いわゆるインディ映画だ。アメリカって奥深いよな、と思う。大金を稼ぐビッグバジェットの大作が世界中に公開される一方で、若くて無名の監督、あるいは長いキャリアをインディ界で過ごしてきたような映画人が、けれん味やハッタリとはほど遠い、地味で静かに心を揺らす作品を作り続けている。それが海を渡って日本まで来て、、近所のTSUTAYAの「旧作」の棚に収まり、僕に発見されるのを待っている。なかなかドラマチックなのだ。

◆「カーズ2」(2011) CARS 2
一作目は飛行機で見て泣きまくった。シンプルで良い作品だった。「ドク・ハリウッド」(1991)と同じ話やん、という突っ込みもあろうが、1は傑作だと思う。日本では「ゲド戦記」とぶつかってしまってヒットしなかったらしいが、「バグズ・ライフ」(1998)と並ぶピクサーの傑作だと僕は思ってる。
だけど、2は大変な作品になってしまっていた。007そっくりのスパイアクションとして幕が開き、東京・イタリア・フランス・イギリスを転戦する大旅行映画になっており、人情や友情が溢れかえって感動の雨あられだ。おかげでメインのプロットであるレースがすっかり霞んでしまっている。
こんなモンスターみたいな作品になってしまったのには、いろんな事情が推察される。一つには、もうMGMもソニーも007の製作を続けられない、という映画界の苦境。だったら俺たちがやってやろうじゃん、とピクサーの人たちは思ったに違いない。また「八十日間世界一周」のような虚仮威しで楽しい大作映画もすっかり廃れた昨今、CGならそれができる、だったら俺たちがやってやろうじゃん、というピクサーの人たちの心意気。どこをとっても立派なのだけど、動機が美しいからといって面白い作品になるわけではない。
でも面白い映画なのだった。デフォルメされて登場する車のキャラたち、「元になった車種は?」と見ているだけでも目まぐるしくて楽しい。個人的には、フィアット500がやけに贔屓されてて、ミニ(とくにBMWミニ)は不遇で、名前のあるキャラに起用されていないのが残念だった。ポルシェ911の彼女は今回も可愛い。イギリスのエージェントがアストンマーチンではなくカルマンギアになっているのがなんというか、絶妙に残念だが、マイケル・ケインの声で見たかった(自動再生は吹き替えだった)。そして主人公メーターのキャラがあまりにうざいので、声を充てた山口智充のことまでちょっと嫌いになった。
ていうか、こんなに難解な作品が子ども向けなのだろうか? そもそも日本の若い世代は車離れしており、「ビッグベントレー」なんて洒落は通じない。こんなクルマニアックな作品は楽しむことができないような気がする。ていうか、そもそも変な作品である。絶対成功しなきゃならない超大作なのに、変なのだ。だから、どうしても嫌いになれない。

◆「正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官」(2009) CROSSING OVER
ICEは Immigaration and Customs Enforcement という法執行機関らしいが、「移民税関捜査局」というより「移民と関税に関する執行局」という感じの組織で、上着に「POLICE」と書かれているが警察ではなく、国土安全保障省の下部組織だ。保障省じたいが2002年にできたものだから、主人公の老捜査官ハリソン・フォードは元は司法省の移民局や出入国管理局で働いていたのだろう。いやもしかすると畑違いのシークレットサービス(財務省)出身かもしれない。彼は他の捜査官と違って捕まえた不法就労者に感情移入しすぎ、甘すぎるところがあるからだ。プロっぽくない。
この作品は、一時流行った「複数視点」による群像劇になっている。時間軸をいじるような複雑なことはしていないので見やすい。次々登場する人物たちがどこかしらで接点を持っている、エピソードが間接的につながってひろがっていく様は見ていて心地好い。しかも2時間を切る優秀な編集、大物の起用と、これまで見てきた作品のようにインディ臭さがない。社会的なテーマなのにきちんとアクションシーンなどの見せ場も用意されており、カタルシスもある。
主人公は老捜査官(フォード)、その相棒はイラン人移民。彼の一家は弟が弁護士、父は実業家など、成功者だが、末の妹がはすっぱな行動で、家族の体面を傷つける、と嫌われている。彼女が働くコピー屋の主人は不法滞在者のための偽IDを作っている。そこに頼みに来たのがオーストラリア人の女優志願。いい女(ばんばん脱いでます)。彼女と知り合って、グリーンカード発給と引き替えに身体を求める移民局員(レイ・リオッタ)。移民局員の奥さんは不法就労専門の腕利き弁護士、子どもができないので養子をとりたがっている。養子候補のアフリカ系の幼児。その子に不法滞在者収容所でおとぎ話を聞かせるのがアラブ人の少女……と説明していっても全然わからないでしょうからもうやめます。いや、群像劇っていろいろ作られましたが、この作品は人びとのつながり具合が絶妙で、それもカタルシスの一因になっています。ちょっと重厚さには欠けるかも知れないけど、それも良いです。
ハリウッドの製作現場にも、移民は多い。僕が好きな俳優ではNZのラッセル・クロウ、豪州のニコール・キッドマン、南アのシャーリーズ・セロンなど。監督ではピーター・ジャクソン(NZ)、ギレルモ・デル・トロ(メキシコ)、アン・リー(台湾)、クリストファー・ノーラン(英)など。インディな映画になるともっと外国人監督が増える。世界中の映画作りの才能が、トップリーグであるハリウッドに集まるからだ。
日本のエンタテインメントは、アニメ製作では韓国・中国との関係が深まっているみたいだけど、他になかなか良い話を聞かない。いや、もともと日本の芸能界は在日韓国・朝鮮人のタレント(才能)たちがいなかったら成立しないよ、彼らの力でここまで来たんだよ、という意見もあるだろうけど、それはちょっと議論の意味が違うと思うのでここでは措く。
アメリカの映画業界は世界中から才能を募っており、大きく稼げるのなら何国人だってかまわない、チャンスを与えよう、という基本姿勢があるようだ。大好きなアン・リーは「ハルク」(2003)で大失敗したりもしたが、結局堂々たる大物監督になった。「ラスト、コーション」(2009)では全編中国語で、ある意味故郷に錦な大作だよね。きっと中国人映画ファンから大集金したことだろう。ともかく、立派におなりになった。
本作に登場する女優志望の豪州女性、キッドマンとかも駆け出しの頃はこんな苦労をしたんだろうな、と思わせる。そしてクライマックスは、連邦地裁判事が司会する移民たちの宣誓式。「あなた方は自分の意思でアメリカ市民になるのだ」と繰り返し宣する。これは本当に、世界でも特異なシステムだと思う。アメリカという国の活力の素だし、混沌の素でもあろう。そして、この宣誓式に来れなかった何人もの登場人物たちを思い浮かべる。社会のいろんな位相を描こうとする、意欲作だと思う。ちょっと脚本が破綻したとこもあるけど。
ところであの宣誓式、どの州でもやるのかな? 古い友人がグリーンカード取ってアメリカに移住したんだけど、やっぱり宣誓式出たのかしら。こういう、“めったに見られないもの”を見せてくれるのが、良い映画の条件の一つだと思っています。
【追記】
“アメリカに移住した古い友人”から、お便りをいただいた。ありがとうございます。
「正義のゆくえ」に出てくる「宣誓式」「グリーンカード」のことを僕は誤っていた。正確にはこうなのだそうだ。
あの「宣誓式」ですが、あれは市民権を取得して合衆国市民になった人が出席するものです。
永住権=市民権ではありません。市民権を取得するためには永住権取得後、米国に5年以上居住することが必要で、5年以上居住すると市民権を取得するための権利が生まれます。その後、アメリカの歴史や一般常識に関する試験があって、これに合格すると晴れてアメリカ合衆国市民となれるわけです。
でも、5年以上アメリカに住んでいる人がすべて市民権申請をするかというと、そんなことはありません。
たとえば、日本人で市民権申請(嘆願書の請願)をする人はほとんどいません。それはなぜかと言うと、日本の法律が二重国籍を認めていないからです。日本の国籍を放棄してまで、市民権を取得しようとは思いませんよね? 年金受給資格とかも失ってしまうわけですから……。
私の知り合いのフランス人でハワイ在住の人がいますが、彼はフランスとアメリカのパスポート両方持っています。母国が二重国籍を認めていれば、これは市民権取得したほうが有利ですよね。年金とかも両方の国からもらえるわけですから。
ということだと。ありがとうございます。
この作品には、グリーンカードを求めて右往左往する人たち(女優志願の豪州女性、ヘブライ語の話せないユダヤ人青年)、アメリカの市民権を求める人たち(韓国人クリーニング屋一家、フォードの相棒のICEエージェントの父)などが描かれるが、それぞれ事情の位相が違ったんだね。